「聞く読書」や「オーディオブック」に興味はあるけれど、どんなものかわからないので始められない…という方も多いのではないでしょうか?
私は「聞く読書」を3年間続け、その良いも悪いも両方を経験してきました。
この記事では、その実体験をもとに「聞く読書」のメリット・デメリットを詳しく解説します。
さらに、デメリットを克服する方法もご紹介しますので、「聞く読書」を効果的に活用したい方はぜひ参考にしてください。
【聞く読書】とは?
「聞く読書」とは、オーディオブックやスマートフォンの読み上げ機能を活用し、耳で本の内容をインプットする読書方法です。
特に、Audible(オーディブル)やaudiobook.jpといったオーディオブックサービスが人気です。スマホやタブレットがあれば、いつでもどこでも読書ができる点が特徴です。
【聞く読書】のメリット
では早速、メリットを紹介していきます!
メリット1:「ながら読み」でスキマ時間を活用できる
「聞く読書」最大の特徴は、なんといってもその手軽さ。スマホ1台あれば目や手を使えない状況でも読書が可能になります。
かく言う私も、これのポイントに一番のメリットを感じて読書漬けになっているひとりです。
・通勤・通学中
・ジョギングや散歩の最中
・家事をしながら
・庭仕事をしながら
・お風呂やリラックスタイム
このように、ほかの作業と同時並行で読書ができるため、多忙な方にこそおすすめの読書法です。
メリット2: 難しい本に挑戦しやすい
紙の本では挫折しやすい分厚い本でも、「聞く読書」ならスムーズに進められます。
実際に私も「聞く読書」をするようになって初めて400ページを超える本を読破することができました。
難しい本を読むときって、単語1つを読むのにもつまづいしまって、スムーズに読み進められない時がありますよね。「聞く読書」を活用すれば、そのような場面で逐一止まらなくて済むので、スラスラ読み進められます。
「聞く読書」は難しい本を読むときサポートをしてくれる存在なんです。
特に、専門書や哲学書、分厚い小説を読むときは心強いです。
メリット3: 目が疲れない
長時間の読書で目が疲れることはありませんか?
「聞く読書」なら目を使わないので、目の疲労はぐっと減ります。
特に昨今、電子書籍で本を読む人も多く、目疲れが悩みの種だと思います。
私も、紙の本では半日くらい平気ですが、電子書籍だと2時間も本を読むと、目に疲労を感じるようになります。
「聞く読書」なら、
・ブルーライトによる疲労軽減
・ドライアイ対策
にもなります。
メリット4: 正しく発音・言葉を理解できる
自分で本を読むと誤読してしまうことがありますよね。
私は、誤読魔なので、漢字の読み間違いはもちろん、カタカナの人物名なんぞは似ているものが続くと、区別するのにひと苦労です。
「聞く読書」なら正しい発音やイントネーションで聞けるため、言葉の理解が深まります。似ている言葉も、文字だけで読むより判別が簡単です。
さらに英語の学習の場面では、オーディオブックを活用すれば、リスニング力の向上にもつながります。
ただし、「聞く読書」の中でもスマートフォンの「読み上げ機能」を使った読書では、誤読の可能性があるので少し注意が必要です。
メリット5: やる気が出なくても読書にとりかかれる
当たり前ですが、普段、本を読むときは、自分で文字を追わないと読み進められません。
「読む」という行為は、実はとても自発性が要求される行動なのです。
だから、本を読むのってちょっと気合がいるし、心の余裕がないと、なかなか取り掛かれないものです。
それを少し楽にしてくれるのが「聞く読書」です。
なにせ、自分が意識していなくても、勝手に文章を読み上げていってくれます。普通に読むよりも少ない集中力で読書をすることができるのです。
読書のハードルが下がれば、面倒くさく感じにくくなり、読書をする機会が増えます。
【聞く読書】のデメリットと対処法
次にデメリットの解説です。対処法も一緒に記載していますので、ご活用ください!
デメリット1:内容を読み返しにくい → クリップ機能やメモを活用
特にAudibleやオーディオブックなどの音声サービスを使った「聞く読書」の場合。
利用できるのは、音声だけなので、文章で確認する、といったことができません。
読み返したいときは、何章目のどの辺だったか記憶をたどらないと、振り返るのにも一苦労です。
【対処法】
Audibleには「クリップ」機能があり、気になる箇所にしおりをつけることができます。
また、Kindleの電子書籍サンプルをダウンロードし、目次と照らし合わせるのもおすすめです。
また、おすすめなのが、無料の目次を活用することです。
Kindleなどで電子書籍のサンプルを無料でダウンロードし、それを地図のように使って、見返したい箇所を探すのです。目次の羅列を見て、どんなことが書かれていたか思い出すこともできるので、記憶の定着にもとてもいいのです。
Audibleにも表示される目次でもいいのですが、
本によっては、大きな章立てのみで小見出しが表示されない場合も多く、見返しには不向きです。
デメリット2:耳が疲れやすい → 紙の本と交互に読む
「聞く読書」は目が疲れにくい代わりに、耳が疲れにくいです。
イヤフォンなどのデバイスを利用している場合、さらに疲れやすいです。
散歩やジョギングなど、外で「聞く読書」をしている場合は、車などの音にかき消されないように音量を上げるので、ますます疲れやすくなります。
【対処法】
まずは耳が疲れてきたら、疲労のサインだと思って休むことをおすすめします。
それでも、どうしても切り上げられない、という場合は、休憩がてら目で読書をするといいでしょう。
聞く読書→見る読書→聞く読書
と感覚器官を切り替えて読書をすると疲れを分散させやすいです。
デメリット3:マルチタスクで脳が疲れやすい → 過労のサイン&休憩
「聞く読書」は耳が疲れやすいのに加え、頭も疲れやすいです。
これは、メリットである「同時作業ができること」の弊害でもあります。
同時作業ができるということは、マルチタスクになりがちだからです。
マルチタスクは注意力散漫になりやすいので、脳の疲労速度がシングルタスクの時の2倍、3倍になります。
この状態で無理に読書を続けても、集中力が半減していて、大したパフォーマンスは出せません。
【対処法】
あたまの疲れを感じたら、この時ばかりは潔く休憩&リフレッシュしてください。
おすすめは
・お風呂でリラックス
・ストレッチ
・瞑想
脳の疲労は、頭を使いすぎているのが原因なので、体の感覚を養うようなリフレッシュ方法が良いです。
私は、入浴すると頭がボーっとしていたのが一気にスッキリします。
シャワーだけでも効果があります。
デメリット4:図表の多い本は向かない → 紙や電子書籍で読む
図を見ながら読むを前提に構成されている本は、「聞く読書」だけで理解するのはかなり難しいです。
単語や固有名詞が多く出てくる本も、言葉をひとつひとつ覚えながら読み進めたり、読者の頭で文を体系立てて理解することを求められるので、聞く読書だけでは限界があります。
特に、資格試験・会計・理系の本などに多い印象です。
このような図やグラフが重要な書籍は「聞く読書」には不向きです。
【対処法】
こうした本は「聞く読書」で読むのをキッパリやめましょう。
「聞く読書」に向かない本に非効率的な時間を費やすより、
「聞く読書」に向く本にたくさんの時間を使いましょう。
この世にはたくさんの本があります。
場面や方法に適した本を効率的に読んでいきましょう。
なんやかんや「聞く読書」を続けていけば、
紙で本を読む習慣が出来上がるので、「聞く読書」で読みにくい本もいつか読めるタイミングが巡ってきます。
「この本は聞く読書ができないから駄目だ・・・」などと落ち込む必要はありません。
デメリット5:読むスピードが遅い → 再生速度を調整
目で本を読むより、「聞く読書」の方が、1.5~2倍の時間がかかります。
文を一つ一つ読み上げているので、当たり前と言えば当たり前ですね。
数字だけ比べてみると、時間がかかってわずわしいと思われるかもしれませんが、この時間の差は、実はあまり気になりません。
むしろ、小説では細かい描写をひとつひとつ味わって聞けたり、
実用書では重要な情報を読み飛ばさずに済んだりと、「読書の質」が高まって良いことの方が多い気がします。
「急がば回れ」といったところでしょうか。
【対処法】
どうしてもスピードアップしたい場合は、再生速度を調整しましょう。
私の場合、
・小説:2.0~3.5倍速
・情報系:1.5倍速以下
が自分に合った速度です。
自分に合った速度を探って設定してみましょう。
デメリット6:バッテリー消費が激しい → 音声サービスを利用
スマートフォンで利用している以上、バッテリーの問題が付いて回ります。
特にスマートフォンの「読み上げ機能」を使った聞く読書では、とんでもなくバッテリーを消費します。
朝フル充電だったものが、お昼ごろにはバッテリー20%を切ってしまうほど、消耗が激しいです。
【対処法】
スマートフォンの「読み上げ機能」はバッテリー消費が激しいですが、
Audibleなどの音声サービスなら音楽を流すのと同程度の消費量で済みます。
日中ずっと音声を流していても、せいぜいバッテリー40%まで落ち込む程度です。
最強の読書術は【普通の読書】×【聞く読書】の相乗効果
「聞く読書」のメリット・デメリットを並べていると、どうしても
「普段の読書と比べて、結局どっちがいいの?」という思考になりがちです。
そこで私が声を大にして主張したいのは、
「どちらか一方ではなく、どちらも両方活用することこそが、良いところ取りの最強の読書術」だということです。
「聞く読書」は目で読む読書と組み合わせることで、学習効果を何倍にも高めることができるのです。
例えば、資格試験やビジネス書を読む場合、
・まずオーディオブックで全体を把握
・紙の本で細かい部分を理解&見直し
という流れで進めると、効率的に知識を定着させることができます。
同じ本を「聞く」「読む」の2つの方法でインプットすると、記憶に残りやすくなるのです。
特に学業や資格などの本については、絶大な威力を発揮します。
「同じ本を2回買うのは、お金がもったいない」と思われるかもしれません。
し電子書籍を購入し、スマートフォンの「読み上げ機能」を活用した「聞く読書」であれば、購入は1回で済みます。
KindleUnlimitedとAudible、2つのサブスクサービスで共通して取り扱いのある書籍を選ぶ、という方法もあります。
工夫すれば、コストは抑えられますので、ぜひ一度試してみてもらいたいものです。
まとめ
「聞く読書」は、忙しい現代の私たちにとってにぴったりの読書方法だと思います。
といったメリットがある一方で、
といったデメリットも存在します。
しかし、ご紹介した適切な対策をとれば「聞く読書」を最大限活用できます。
「目で読む本」と「聞く読書」、どちらもバランスよく取り入れて、より充実した読書体験を楽しみましょう!
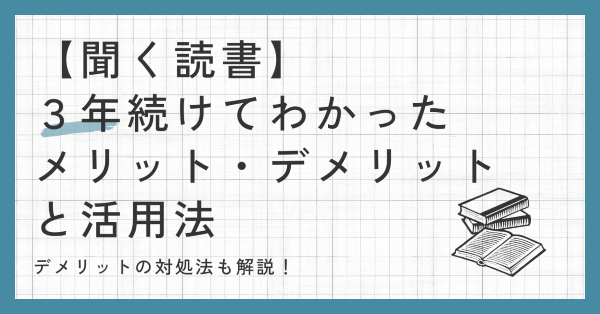
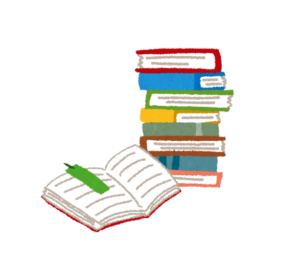
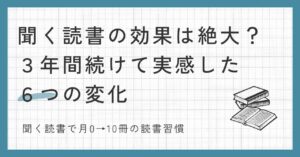
コメント